こんにちは。ゆきこです。
今回は最近ビジネス書でよく取り上げられている素敵な書籍を紹介します。
私はずっと考えてきました。
どうすればみんなが幸せになれるのか。
そのために必要な能力は一体何なのか。
どうすれば身につけることができるのか。
GRIT(やり抜く力)はその答えの一つの示唆している良書でした。
多くの人にとって役立つ能力としてやり抜く力の重要性を説いています。
人生をより充実した幸せなものにしたい。
目標を設定してもなかなかやり通せない。
子どもにはたくましく育ってほしいが育て方がわからない。
そんなお悩みを抱える方には最適な一冊だと思います。
興味のある方は是非その概要を一緒に見ていきましょう!
人が学ぶべき重要な能力
偉業を成し遂げる人や、大きな目標を達成する人には、どんな能力が共通しているのでしょうか?
私はこの問いについて頻繁に考えます。
と言うのも、私は地元の国立大学出身です。
勉強だけが取り柄な真面目な人柄で、それなりに頑張ってきたと思います。
にもかかわらず社会に出て鬱病になり、今は働けない状態です。
学校教育で上位であった私にとって今の状況は非常にもどかしい気持ちなのです。
つまり今の学校教育で身につけられる能力では、社会で生き抜くには不足していると言えますよね。
勉強ができても大した意味はないと落胆してしまいます。
では一体私は何を学び、習得すれば良かったのでしょうか?
その一つがやり抜く力だと書籍では語られています。
そしてやり抜く力は次の二つの要素に分けて考えることができるそうです。
やり抜く力=情熱×粘り強さ
私は勉強が特別好きだったわけではなく、学ぶことに情熱を持っていたわけでもありません。
ただ与えられたから受身姿勢で言われた通り勉強して良い評価をもらっただけでした。
そしてたまたま理解力や記憶力が人より優れていて、学習が早く身についたのです。
授業だけで内容が理解でき、テストまで覚えていられる、と言うだけでした。
つまり私は勉強こそできても、情熱もなければ粘り強さもない、やり抜く力のない人間だったのです。
この事実を痛感したことで、私が今までやってきたことがあまり意味のなかったものに思えて少し悲しくなりました。
今思えば、多趣味でもどれも中途半端で、大きな成果を出す前に辞めてしまうことが多かったと思います。
囲碁将棋、ゲームプログラミング、3DCG、ピアノ、ギター、ヴァイオリン、作曲、コーチング。
大学までは単位を取得する半年間頑張れば良いだけなので、比較的何とかなっていました。
それが何年もかけて熟達していく社会人の生き方に馴染めず、部署の異動も頻繁にあって専門性を高められませんでした。
今ここで再認識するべきは、やり抜く力を今からでも磨いていく必要があると言うことです。
それが鬱病を治し、発達障害と向き合っていく糧になると感じました。
やり抜く力は伸ばせる
人はよく「才能」という言葉を使います。
自分には到底できない成果を目にして、あの人は才能があると考えるようです。
これは生まれ持った特別な能力のある人、を意味する言葉だと思います。
しかし私はこの考え方にある意味反対の意見を持っています。
もちろん遺伝的に決まったものもあります。
身長や持病の有無、身体的な特徴などは才能と言えるかも知れません。
ですが社会で生きていくために必要な能力の多くは、後天的に身につけられるものなのです。
つまりは努力がものを言うということです。
才能と言う言葉は、自分にはできないほどの努力を生まれ持ったものだと軽視する逃げの考え方です。
大きな成果を生み出す人は、必ず一般的な人よりも何倍も努力しているはずですよね。
結果だけ見て才能だと言っていては物事の本質は見えてきません。
結果を出すためにどれだけの試行錯誤、努力、工夫、忍耐があったかを深く考える必要があると思います。
書籍でもこの点については強く言及しています。
やり抜く力は後天的に伸ばすことができると研究から明らかにされたことを述べていました。
その方が希望が見えてくる気がします。
生まれつきの敗北者ではなく、これからの努力次第で人生が変えられると私は思いたいです。
やり抜く力を内側から伸ばす4ステップ
では実際にどうすればやり抜く力を伸ばすことができるのでしょうか。
書籍では大きく4つの要素が影響していると述べられています。
「興味」「練習」「目的」「希望」
これらについて具体的に考えてみましょう。
興味がなければ続かない
人にはそれぞれ興味関心のある分野が違います。
それは当たり前のことですし、否定することはありません。
ですが学校教育では決まった科目しか学ぶことができませんよね。
これでは自分が本当に興味のある分野を発見することができません。
私は大学に入って情報系を学びましたが、教育に興味が出てきて、教育学部に潜入して研究室に混ぜてもらいました。
そして経営に興味が出て金融機関に就職しました。
これらは学校教育では知らなかった新しい分野であり、もっと早く出会っていれば進路や生き方が違ったと思います。
教育心理学の研究者になっていたかも知れませんし、MBAを取得して経営コンサルタントになっていたかも知れません。
私は自分が得意だったからと情報系に進学し、SEとして仕事をしました。
ですができることと興味があることは違います。
パソコンができるからと言って、パソコンの専門家として生きていきたいとは全く思わなかったのです。
そして人事、経営企画、SDGsと部署を転々として鬱病になり退職しました。
人は興味がないことを続けられない生き物なのです。
もちろん漠然とした気持ちで淡々と取り組むことはできるかも知れません。
ですが情熱を持って、やりがいを感じながら粘り強く取り組むのは興味がなければ難しいでしょう。
特に私は発達障害の特性でこだわりが強かったため、興味がないことには全く力が入りませんでした。
金融機関時代には、SEの仕事には関係のない資格試験を強制され、全く合格できずに苦しんだ経験があります。
興味関心の幅が狭くどれだけ机に向かっても勉強できませんでした。
学歴があるのに資格が取れないことで社内ではかなり責められました。
勉強できるのにサボっているだけだと罵られることばかりです。
でも興味がない、納得できないことには取り組めないんです。
結局発達障害、鬱病と診断されるまでこの苦しみは続き、診断されてからも心苦しさは残りました。
練習しなければ能力は磨かれない
私は自転車に乗れるようになるのが遅かったです。
中学生になって自転車通学が必須になることがわかった小学校高学年でやっと乗れるようになりました。
発達障害の特性で身体の使い方が不器用だったのもあります。
ですが練習するのが嫌だったのが一番の要因です。
自己啓発書などでは、一流になるには1万時間費やして専門性を磨くべきだとよく書かれています。
ざっくり計算すると仕事で5年はかかりますよね。
つまり大きな成果を出す人は、ただならぬ練習をして自分を磨いているということです。
私は就職して配属されたシステム課から、1年で人事、経営企画、SDGs室と転々としてきて、何の成果も出せないまま退職しました。
長期間一つのことに取り組むと、最初は新しい知識や技術を得て成長を簡単に実感できます。
それが成熟していくと同じことの繰り返しになってしまう場合が多いと思います。
大きな成果を出せる人とそうではない人との違いは、微妙な変化を読み取れるかにかかっています。
ただ漠然と同じことを繰り返すのではなく、小さな成長を追い求め続けることが重要だと述べられています。
学生時代に認知心理学を学んでいた際、職人は機械でも測定できない微妙な誤差を見極められると聞きました。
これが大きな成果を出せるプロフェッショナルなのだと今思えば納得できます。
やり抜く力を身につけるには、長い間練習を重ね、専門性を磨いていく必要があると言うことです。
興味のあることを続けるうちに、やり抜く力が醸成されていくと説明されています。
目的が人を動かす
ただ自分の興味関心だけを動機に大きな成果を出せるのでしょうか?
偉大な研究者はその知的好奇心で世紀の発明を生み出したのかも知れません。
ですが実際には成果を出すためには、多くの人と関わることになるはずです。
そういった人たちがやり抜く力にどう影響するかも重要なポイントだと思います。
何かを成し遂げるには、周囲からの応援や支援が不可欠です。
つまり他者をいかに仲間にしていくかが重要になります。
そこで必要なのが目的です。
大義名分と言っても良いかも知れません。
自分の個人的な興味関心のためだけではなく、誰かのため、社会のため、という目的意識が周囲の人を動かし、結果としてやり抜く力を後押しすると考えられます。
自己中心的な人には誰もついてきません。
口だけでは良いことを言っていても行動が伴っていなければ信用できません。
興味関心を持って、練習に熱心に取り組み、大義名分を掲げて頑張るから成果が出せるのです。
これらの要素が一貫してやり抜く力につながっていることがとても理解できました。
希望が粘り強さの土台となる
最後の4つ目の要素は全体に大きく影響するものです。
失敗や挫折を経験した際に、立ち上がるモチベーションになるもの、それが希望です。
自分ならできる、努力は報われる、と思えるかどうかで結果は変わっていきます。
私は自分には価値がない、どうせ上手くいかないと考えてしまいがちで、なかなか行動が続きません。
例えば営業職の人で、何度も断られると心がくじけてしまう人もいると思います。
私だったらとても営業なんてできません。
ですが絶対に自分が役に立てる人がいる、必ず成果を出せるまで頑張る、と希望を持てている人なら、諦めることなく努力を続けることができるのだと思います。
鬱病だとこの希望を持つことが非常に難しいです。
思考がどんどんネガティブな方向に進んでしまうからです。
時には周囲の人を頼っても良いかも知れないですし、自分で気持ちを切り替える術を身につけるのも良いと思います。
私は認知行動療法をこれから取り入れていこうと考えています。
少しでも自分の考え方を選択できるようになれば、現状を打破する糸口が見つかるかも知れないと思っています。
これが今の私の僅かな希望です。
まとめ
書籍ではやり抜く力を外側から伸ばす方法、つまり教育する側の視点からの考察も多く述べられています。
今回は私自身がやり抜く力を身につけたいと考えていたので、内側からの内容に絞って解説していきました。
やり抜く力、本当に大事です。
少なくとも学校教育の5教科よりは学ぶ価値があると私は感じました。
そして私が鬱病を克服し、発達障害とも向き合って生きていくには、やり抜く力が不可欠だと痛感します。
このブログの最終目標である、ブログだけで生計を立てる、を実現するためにも、情熱と粘り強さを持って取り組んでいきたいと思いました。
とても興味深い内容ですし多くの方が役に立てること間違いなしの良本ですので、是非読んでみてください!
最後までお付き合いくださりありがとうございました。


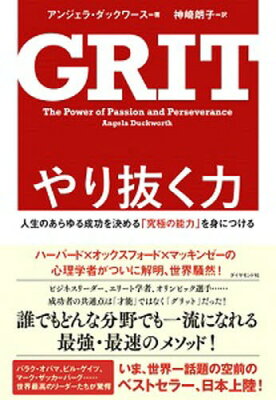






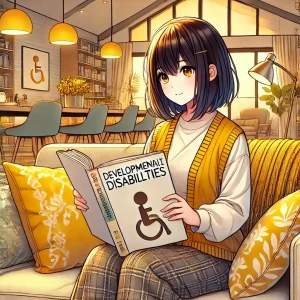


コメント